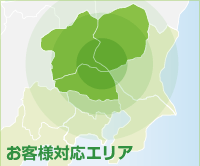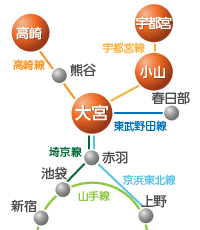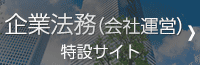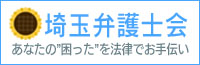弁護士に依頼するメリットとデメリット(何をしてくれるのか?弁護士が必要な理由は何か?)
弁護士に依頼したいけれど、弁護士は司法書士や行政書士とどう違うのか?
弁護士に依頼することにはどのようなメリットがあるのか?
法律問題でお困りの方の中には、このようなことでお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今回は、弁護士と司法書士・行政書士との違いや、弁護士に依頼するメリット・デメリットについて解説します。
1 弁護士とは?弁護士と司法書士・行政書士との違い
弁護士に依頼するのはハードルが高く、司法書士や行政書士に依頼したいと考える人も少なくありません。
確かに、弁護士と司法書士・行政書士は、いずれも法律関係の資格保有者ですが、それぞれができる業務の範囲・保有している権限に大きな差があります。
以下では、弁護士・司法書士・行政書士それぞれについて、どのような権限を持っていて、どのような業務ができるのかなどについて解説します。
1-1 弁護士とは
弁護士は、法律や裁判所スペシャリストで、金銭トラブルや離婚、相続や遺言、交通事故、債務整理、刑事事件などあらゆる分野の法律問題を取り扱う権限があります。
以下に述べる司法書士や行政書士のように、法律分野であれば、取り扱える業務に制限はありません。
1-2 司法書士とは
司法書士は、本来的には登記の専門家で、登記や供託に関する手続の代理が典型的な業務です。原則として、有料で、弁護士が行う法律行為の代理をすることも法律相談をすることもできません。
ただし、法務大臣の認定を受けた場合には、例外的に訴額140万円以下の簡易裁判所での訴訟代理権が認められます。現在は、簡裁代理権を有している司法書士も相当の数に上っています。
しかし、簡裁代理権を有する司法書士であっても、事件の依頼には以下の点に注意が必要です。
- 金額が140万円を超える事件については代理権がない。
- 相談の途中に140万円を超える事件であることが判明した場合には、司法書士は直ちに法律相談や交渉を中止する必要がある。
- 離婚や相続などの家庭裁判所の対象事件は受任できない。
- 破産事件は受任できない。
- 簡易裁判所の事件でも、地方裁判所に移送されたり、控訴された場合には司法書士は代理権を失う。
1-3 行政書士とは
行政書士の本来的な業務は、「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」です。
これに付随して書類の代理提出や作成の代理、書類作成に関する相談に応じることはできますが、事件についての示談交渉や裁判手続きを行うことはできません。また、報酬を得る目的で法律相談を受けることもできません。
したがって、当事者間で争いがあったり、争いが生じる可能性がある案件の書類作成に携わることはできません。
1-4 司法書士や行政書士が権限外の行為をした場合
簡易裁判所の訴訟代理権がある司法書士が140万円を超える事件の代理人をしたり、離婚や相続の代理人をしたりした場合、あるいは行政書士が法律を得る目的で法律相談をしたり、争いがある事件で交渉を行う書類を作成した場合は、「非弁行為」に該当するとして処罰対象になります。
非弁行為とは、弁護士でない者が弁護士しかできない法律事務を行うことで、これを行うと2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることになります。
それだけでなく、司法書士や行政書士が行った非弁行為に該当する法律事務は無効になる可能性があり、依頼の目的を達せないことにもなりかねません。
そのため、「費用が安いから」という理由で、安易に司法書士や行政書士に法律問題を依頼することには注意が必要です。
2 依頼を決めている場合でも、迷っている場合でもまずは法律相談
離婚や相続、借金などの法律問題があり、弁護士に依頼しようと決めた場合でも、依頼しようかどうか迷っている場合でも、ひとまず弁護士に法律相談をすることをおすすめします。その理由は以下のとおりです。
2-1 弁護士に依頼する必要があることかどうかがわかる
弁護士に法律相談すると、自身が悩んでいることが弁護士に依頼する必要性が高いものなのか、自分でも解決できることなのかがわかります。
法律相談をして弁護士の助言を聞くことにより、事の重大性や解決までの道筋の複雑さ・煩雑さの程度を知ることができます。
これらを知らないまま弁護士に依頼すれば、簡単なことで高額な費用を支払うリスクがありますし、逆に、難しい対応を迫られてどうにもできなくなることもあります。
そのため、まずは弁護士に相談することが望ましいといえます。
2-2 弁護士との相性が判断できる
弁護士の法律相談は一般的に30分程度です。
30分も話をすると、その弁護士の話の仕方・聞き方、問題の解決方法などがわかり、相談者との相性も判断できます。
相性が良いと思ったら依頼をすればよいですし、相性が良くないと考えたら、また別な弁護士に相談すればよいということになります。
法律相談をせずに弁護士に依頼を決めてしまうと、相性が合わない弁護士と付き合うこととなり、心労がさらに募ります。
この点においても、まず法律相談を行うことが大切です。
2-3 解決の方向性がわかる
弁護士に法律相談をすることにより、問題となっている件について、どのような道筋で解決することが可能かわかります。
方向性がわかることにより、不安が和らぎ、弁護士に依頼した後の進行状況も理解することが可能となります。
法律相談をせずに依頼をすると、解決の方向性がわからず、かえって不安が募ります。
この点でも事前の法律相談は重要です。
3 弁護士は何をしてくれるのか:依頼のメリット
では、実際に弁護士に依頼した場合にどのようなメリットがあるか解説します。
3-1 相手方に対する窓口をなってくれる
弁護士に依頼する最大のメリットは、相手方に対する窓口になってもらえることです。
弁護士は依頼を受けたあと、相手方に対して受任を知らせる「受任通知」というものを送付します。
この通知には、今後の連絡先が弁護士であること、当事者に直接連絡しないでもらいたいことが記載されています。
その効果として、相手方がよほど問題がある人物でない限りは、弁護士に対応してもらうことが可能です。また、受任通知発送後も相手方が当事者に直接連絡をしてくる可能性がある場合には、弁護士が対策を考えてくれることも少なくありません。
例えば、離婚の場合は配偶者への対応を、債務整理の場合には債権者への対応を弁護士に任せることができます。
紛争の相手方への対応はとてもストレスが大きいものなので、対応の窓口になってもらえることは、とても大きなメリットといえます。
3-2 自分の主張を法律的に組み立ててもらえる
弁護士に依頼せずに自分で法律問題について対応しようとしても、自分の主張が法律的にどう位置づけられるのかわからず、交渉相手や裁判所になかなか理解してもらえないということも少なくありません。
弁護士は法律問題の専門家なので、依頼者から事情を聴けば、それを法律的に組み立てて主張することが可能です。
そうすることにより説得力が増し、相手方との交渉や裁判所とのやり取りもスムーズに行くことになるため、この点も弁護士に依頼するメリットの1つということができます。
4 弁護士に依頼するデメリット
弁護士に依頼する最大のデメリットは、弁護士費用がかかるということです。
弁護士費用については、かつて統一基準がありましたが、現在は自由化されており、事務所ごとに弁護士費用が異なります。
弁護士によっては、問題となっている案件に対する弁護士費用や成功報酬が高額となり、費用倒れに終わる場合もあり得ます。
そのため、弁護士に依頼する場合には、どの程度の費用がかかるのかを必ず確認する必要があります。
*当事務所の弁護士費用の考え方については、以下のサイトをご覧ください
https://www.tsukasa-law.net/info/fee.html
5 まとめ
弁護士に依頼する場合には、ある程度の弁護士費用がかかるものの、司法書士や行政書士ができないことをしてもらうことができ、依頼するメリットも高いことがお分かりいただけたと思います。
当事務所は、不当に高額な費用を請求することはありません。費用に関するご相談には柔軟に応じます。
法律問題でお困りの方は、是非一度当事務所にご相談ください。